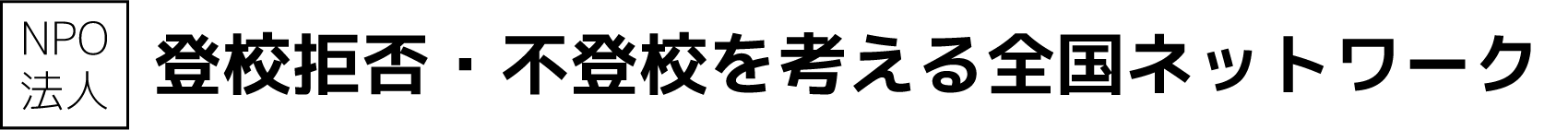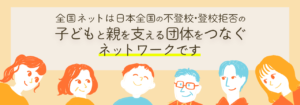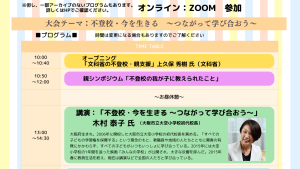GW明け、学校を休みたいと子どもが言ってくれたときのおとなの対応に関する注意喚起の共同声明を「フリースクール全国ネットワーク」さん、「多様な学びプロジェクト」さんとともに出しましたことをお知らせいたします。
<< 子どもが「学校休みたい」と言った時の子どもを追いつめる対応に関する注意喚起の共同声明 >>
2025年5月7日
特定非営利活動法人 フリースクール全国ネットワーク
特定非営利活動法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク
特定非営利活動法人 多様な学びプロジェクト
【趣旨】
新年度を迎えた子どもたちの中には、ゴールデンウィーク明けに「学校を休みたい」と訴える子どもがいます。また、頭痛や腹痛を訴える子どももいます。そのような子どもは、4月からの新しい環境に緊張やストレスを抱えてきた子どもで、これからの生活に大きな不安を抱えています。そのような子どもが「学校休みたい」と言ってきたときの大人の対応次第で、子どもは心身に支障をきたすばかりか大人への信頼感を損ない人間関係も悪化します。しかし、子どもに寄り添う対応をすると、子どもは安心感に包まれると同時に、大人への信頼も増し人間関係が良好になるきっかけにもなります。
子どもが「学校休みたい」と訴えてくれた時は心がストレスや不安でいっぱいいっぱいの状態なので、まずはゆっくり休ませてください。大人も不安になると思いますが、まずは子どもの気持ちを最優先にしてください。理由を問い詰めたり感情的になって怒ったりすると子どもは心を閉ざして、例え登校しても勉強も身に付かないどころか自己否定が強くなって自傷行為を行ったり、「消えたい」という思いを持つ子どももいます。子どもの命を守ることを最優先に子どもへの寄添いをお願いします。
多くの大人は子どもから「学校休みたい」と言われたら、戸惑い悩みながらも登校することを強いるでしょう。その心理は「一旦休むとズルズルと休み続け不登校になる」、「休みを許すことは甘やかしで、子どものために厳しく育てなければ」、「勉強が遅れると進学に影響してどんどん落ちこぼれる」、「学校へ行けない子どもは将来、社会に出ていけない」などの思い込みや刷り込みから起きていると思われます。不登校が増えている近年、そのような発言がメディアに取り上げられることを危惧しています。
私たちは、多くの「不登校をしたけど笑顔で生きている子ども若者」を知っています。休むことで心身ともに安心し、意欲も主体性も取り戻し自分らしく生きている子ども若者を知っています。その子どもたち若者たちも「学校休みたい」という思いを大人に受けとめ寄り添ってもらえたからこそ今があります。
学校に行くことが苦しい子どもが勇気を出して「学校に行きたくない」と言ったとき、一番絶望を感じる対応は大人の価値観や思い込みで登校を強いることです。一番安心できるのは子どもの心を尊重し思いを受けとめること(休ませること)です。その安心感の中で意欲も湧き将来の笑顔にもつながります。
「学校休みたい」という子どもに笑顔が消えていたら、まずは休むことを受け入れてください。
【具体的なお願い】
(1)子どもが「学校休みたい」と言ったときに登校を強いない。まずは休ませてください。
○「学校休みたい」と言われた大人も不安になるでしょうが、理由を問い詰めたりせずに「子どもの命を守る」という意識でまずは休ませてください。国が定めた教育機会確保法の第十三条でも子どもの「休養の必要性」が明記されています。子どもが「学校を休みたい」と言ったときこそ、休養が必要なときだと認識してください。
※ 参照:教育機会確保法第十三条
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
○子どもによっては「学校休みたい」と言葉にできず「頭が痛い」、「お腹が痛い」という身体症状で苦しさを訴えてくることがあります。そのような場合も無理はさせずに休ませてください。
(2)家庭がまず安心できる居場所であるようにしてください。
○学校に行かないことに対し将来や成績などに対する不安を煽ったり、ゲームやスマホなど子どものものを取り上げるなどの対応は親子関係を悪化させることにつながります。
○大人の焦りを抑えて、子どもの思いを受けとめてください。
○学校に行きたくない子どもにとって、まず家が安心できる居場所であることを大切にしてください。「家の居心地を悪くすればイヤでも学校に行く」という考えは危険であることをご理解ください。
(3)親の不安を吐き出せる安心できる場を確保してください。
○親の不安は同じ悩みを持つ親同士で出し合うことで軽くなります。どうか、近くの「親の会」に不安を話してください。わかりあえる人と出会えると思います。
○親の不安を煽るような他人の話は真に受けないでください。良かれと思ってアドバイスする人も不登校に対する理解が乏しかったり、自分の価値観を押し付けたりしていることもあります。
○「学校休みたい」と言えるまでに子どもはかなりの時間と勇気を要していますし不安を抱えています。優しい子どもほど「自分は親を苦しめている」と二重の苦しみを背負ったりします。子どもも親も心が軽くなるような親子の時間を過ごすことをお勧めします。
(4)相談は複数の機関にすることをお勧めします。先生方からの相談もお待ちしてます。
○不登校に関する相談も、その子どもその家庭で要因や背景等様々です。一ヵ所の相談結果を鵜呑みにせず複数の機関に相談して自分にあった相談先を見つけてください。
○不登校の相談で高額な料金を請求するところや、不安を煽ったり決めつけたアドバイスをしたり保護者をも追い詰めるような対応をするところがあるのでご注意ください。
○学校の先生方も生徒の不登校で悩まれたときは学校だけで考えるのではなく、親の会やフリースクール、子どもの居場所などにご相談ください。民間機関は学校と協力して子どもを育むパートナーとして、ともに子どもの最善の利益のために協力したいと考えてます。ご相談お待ちしております。
(5)学校の先生方へ 子どもたち、親たちの気持ちにご配慮よろしくお願いいたします。
無理な「学校復帰」「登校」の促しはお辞めください。
○子どもが「学校を休みたい」と訴え学校に登校しないことは、学校に来なくなるのではないかと不安を感じる先生方も多いと思います。しかしながら「お子さんは引っ張ってでも学校に連れて来てください」「学校に連れて来ればなんとかなります」など登校や学校復帰を迫ることは、親に対してプレッシャーにつながります。親は子どもと先生との板挟みになり、辛い思いをします。
まずは子どもや親の気持ちを受け止め、学校主導で進めるのではなく子どもの気持ちを第一に尊重していただきたいと思います。
〇学校に行けなくなって一番辛い思いをしているのは子どもであり 親です。甘えや怠けという見方ではなく、むしろ「学校に行きたくない」と親に言える親子関係であることを評価していただけたらと思います。
〇無理な促しで、表面的には学校に行けたとしても、心は傷ついたり、信頼が壊れてしまうことがあります。学校に行く、行かないといった見方ではなく、苦しんでいる子どもたち、親たちの心に寄り添った対応をしていただけたらと思います。